 つながっていく情熱のバトン。事業と社会貢献活動の両輪で切り拓く、よりよい未来
つながっていく情熱のバトン。事業と社会貢献活動の両輪で切り拓く、よりよい未来
2025年7月10日

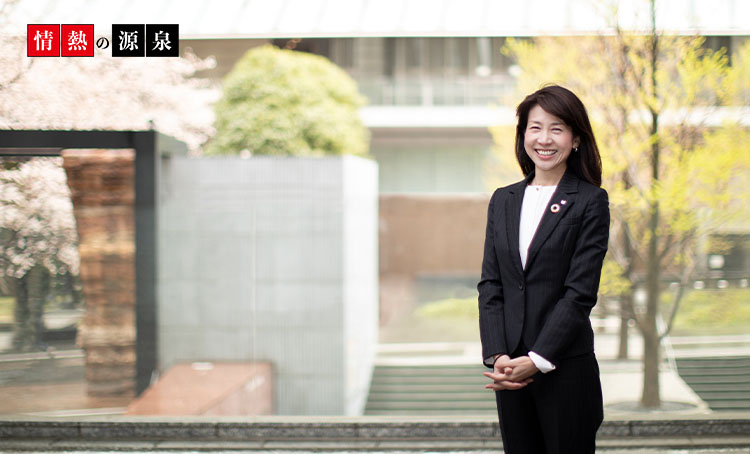
キヤノングループが掲げる企業理念「共生」のもと、キヤノンMJグループは、事業を通じた社会課題の解決に取り組むとともに、創業時から一貫して社会貢献活動にも力を入れてきた。
現在、キヤノンMJグループだからこそできる社会貢献活動を日々追求し、実行しているのが、企画本部 サステナビリティ推進部の広田 由実子だ。入社後はセールスサポートとしてキャリアを積んできた彼女が、社会貢献活動の担当になったのは2019年。「社会貢献活動の世界には、熱い想いを持って活動されている方が多いんです。そのような方々から情熱のバトンを受け取っています」と笑顔で語る広田の情熱の源泉に迫った。
金銭的対価を求めない社会活動だからこそ評価軸が必要
近年、企業の社会的責任の捉え方が大きく変化している。かつての慈善活動やボランティア活動といった事業以外の余力で行う活動と異なり、「持続可能な開発目標(SDGs)」や「ESG(環境・社会・ガバナンス)」の観点を取り入れ、企業の事業活動全体にも関わる戦略的な社会貢献活動へと進化してきた。そこで企業は、地域や国といった社会の一員として、未来創造や社会課題の解決にどう貢献するのかが問われる。
このような潮流の中、2024年に社外公表したグループのパーパス「想いと技術をつなぎ、想像を超える未来を切り拓く」の検討と時を同じくして、2023年にキヤノンMJグループは社会貢献活動の抜本的な見直しを行った。企業としての強みを生かした独自の社会貢献のあり方を模索したのだ。

広田はその経緯をこう語る。
「社会課題が複雑化し、企業の社会的責任も変化する中で、私たちは単なる善行としての社会貢献ではなく、本業の強みを生かした持続可能な活動を目指しました。長年取り組んできたさまざまな活動を見つめ直し、『私たちキヤノンMJグループらしい貢献とは何か』『社会から何を期待されているのか』という観点から徹底的に議論を重ねました」
その結果、社会貢献活動を「キヤノンMJグループの経営資源を活用し、社会のために将来に渡り価値を生み続ける金銭的対価を求めない活動」と再定義した。
さらに広田は続ける。
「これまでの取り組みを、『私たちの強み』と『社会からの期待』の2軸で整理し、五つの重点カテゴリーを設定しました。主に『環境保全』『地域・文化創生』『人材育成』『安心・安全な社会』『健康』を重点カテゴリーと定め、当社の製品や社員の力、パートナーシップを活用したさまざまな取り組みを実施しています。これらはSDGsの目標達成にも連動させています」
SDGsやESG経営の潮流を踏まえつつ、自社の強みを生かした独自のアプローチを追求したというわけだ。あわせて、効果的なリソース配分と活動の質の向上を図るため、評価の仕組みも刷新したという。こだわったのは、単なる社会的義務ではなく、企業と社会が共に持続的に発展するための戦略的な取り組みだ。
「限られたリソースの中で最大の社会的インパクトを生み出すには、一貫した評価基準が不可欠です。この評価軸により、短期的な効果だけでなく、長期的な視点で社会と企業双方に価値をもたらす活動を選択できるようになりました」
キヤノンMJグループだからこそできる社会貢献を追求する
社会貢献活動の対象としている五つのカテゴリーのうち、広田がメインで担当するのは「人材育成」と「環境保全」だ。このほかに、各事業部門の社会貢献活動の評価やPR活動、グループ全体で行う寄付に関する業務も担当している。

では、具体的にはどのような活動を行っているのだろうか。
「人材育成では、将来世代の育成プロジェクトとして、ぺんてる株式会社(以下、ぺんてる)と共同で『校舎の思い出プロジェクト』という取り組みを展開しています。建て替えや統廃合により取り壊しになる小学校の校舎を舞台に、思い出づくりをサポートする取り組みです。校舎をキャンバスに見立て、子どもたちに、壁を大きく使うからこそ描けるような絵を描いてもらったり、それをカメラで撮影して記録に残してもらったりします。取り組みを通じて、子どもたちの学校や地域への愛着や誇りを育んだり、自分たちの思い出深い学校生活を振り返ったり、創造性を刺激したりといった価値提供を目指しています。また、地域の方々に参加いただくケースもあります」
必要な画材などはぺんてるが寄贈し、キヤノンMJグループは、カメラの貸し出し、記念となる大判プリントなどを寄贈している。子どもや地域への価値提供だけでなく、ミニフォトプリンターを利用したイベントなどへの社員ボランティアの参加を募り、地域と社員がつながる機会をつくりだすこともあるようだ。

「これまで、沖縄から北海道まで全国66校で行ってきました。プロジェクトは、1日で終わらせることもできますが、できるだけ授業に組み込んでもらって数日に分けて実施してもらっています。学校全体やクラス単位でテーマを決めて、下描きをして、色をつけて、それを撮影して……と一連の流れをつくりだすことで、作品の完成度を高めるだけでなく、一体感や達成感の醸成にも役立つと考えていますので」
「環境保全」についてはどうだろうか。
「環境保全では、『未来につなぐふるさとプロジェクト』の活動を実施しています。2010年から続いているプロジェクトで、将来世代に多様な生き物を育む美しいふるさとを残すことを目的としています。現在は、環境省の『自然共生サイト』認定のための活動を行っている団体を支援し、一緒に環境保全や環境教育を行っています」
寄付という形で団体を支援する、その原資は回収したトナーカートリッジ等だという。対象団体は専門家と共に検討し、現在は、2024年の能登半島地震により大きなダメージを受けた石川県河北潟の干拓地の水辺植生の復元を目指す「NPO法人 河北潟湖沼研究所」など、三つの団体を支援している。

「自然共生サイトは、現状では申請者の5割以上を企業が占め、NPOや地域コミュニティーの申請が少ない状況です。そのため、キヤノンMJグループでは、認定のための活動をしている団体を支援し、一緒に取り組むことで、より社会のためになるのではないかと考えました。このような形での貢献活動は珍しいかもしれませんね」
そのアイデアにいたったのは、熱い想いを持って社会貢献活動に向き合う人たちと意見交換をしてきたからだという。真剣な彼らの情熱に触れることで、キヤノンMJグループとして何ができるのか、何をすべきなのかを研ぎ澄ませてきた。
「支援が決まった団体とは、年に1回、弊社の社員も参加できるイベントを開催します。社員に参加してもらうことで、自分が勤める会社がどんな社会貢献活動をしているのかを知り、社会貢献について考える機会にもなるはずです」
受け取った熱い想い。その想いの輪が広がり始めた!
社会貢献活動の担当になって6年、「以前所属していたセールスサポートでの業務では、製品やサービスの価値をどうやったらお客さまに届けることができ、対価をいただくことができるのかを考えていました。対価をいただくという意味では、社会貢献活動は180度違う仕事かもしれません。最初は戸惑いもありましたが、今は大きなやりがいを感じています」という広田。大いに刺激も受けているようだ。

「さまざまな立場の方々と接する機会が多いのですが、皆さん、社会的な使命や問題意識に突き動かされて活動していらっしゃる。情熱のある方が多いんです。そのような方々と接することで、社会課題について学ぶことができ、環境をはじめ、自分の周囲のことにも敏感になりました。『課題があるな』と思って終わりではなく、どうやったら解決できるのか、自分に何ができるのか、と一歩前に進む意識を持てるようになりました。それは仕事に限った話ではありません。プライベートでも、自分が『やりたい、やろう』と決めたことに前向きに取り組むことが多くなったと思います。ありがたいことですよね」
活動の思い出もたくさんある。例えば、「校舎の思い出プロジェクト」を開催したある小学校では、不登校だった子どもがプロジェクトをきっかけに「私も絵を描きたい」と、徐々に学校に来るようになったという。
「その子は最初、ほかの子どもがいない時間に絵を描きに学校に来ていました。それを知った友だちが、『一緒に絵を描こう』と、その子が来る時間にあわせて来るように。その輪が少しずつ広がっていったんです。最終的にその子は、学校に通うようになったと聞きました。もちろん先生方の働きかけがあってこそですが、その子の人生に関わることができたのだと考えると胸が熱くなりました」

そんな刺激や感動は、キヤノンMJグループの社員にも波及しつつある。同じく「校舎の思い出プロジェクト」で、社員参加型にしたところ、東京在住の若手社員がボランティアに名乗りをあげた。舞台となるのは北海道の小学校だったが、聞けばその社員は沖縄出身で北海道との縁はないという。さらに、有休を取って自費での参加だ。
「若い世代は、社会に貢献したいという想いが強いと感じます。社会貢献活動に取り組んでいる企業かどうかが、就職先を決める際の主要な理由になることも珍しくないようです。当日、その社員の笑顔を見て、社員参加型にして本当に良かったと企画冥利に尽きましたし、会社が率先して機会提供することの大切さを実感しましたね」
まさしく「情熱のバトン」だ。広田が感じてきた、校舎やそこで過ごした大切な時間に対する先生や児童の熱い想いが、その社員にも伝わった瞬間かもしれない。
「やりたいことは尽きない。猫の手も借りたい」と笑う広田だが、もちろん大変なことや気を使うこともある。
「社会貢献活動との関連性が強いサステナビリティの分野は、グローバルな視点が求められ、さまざまな立場の方と接するので、相手の立場や状況を考えながらお付き合いするようにしています。また、ルールが変更になることも多々あるため、情報のキャッチアップは常に欠かせません」
社会貢献活動を社内外にもっと伝えていく意義
活動の見直しを経て軌道に乗るキヤノンMJグループの社会貢献活動。今後、どのように進化させていくのだろうか。
「まずは引き続き、現在の活動にしっかりと取り組んでいきます。その上で、社内外に対してキヤノンMJグループの社会貢献活動と、そこに取り組む私たちの想いを伝えることに力を入れたいです。セールスサポートの経験からいうと、社会貢献活動がキヤノンMJグループのイメージ向上や地域と関係性を深めるといった価値を生み出すことで、お客さまと接する営業担当者などの活動のサポートにつながれば嬉しい。また、社員自身が自社をより誇りに感じるきっかけになればいいですよね」
例えば、先日社員がボランティアとして活動に参加した様子を動画にして社内に向け公開したところ、大きな反響があった。今後も、どのような形で参加するのか、受け入れ態勢はどうするのかなどの課題をクリアにしながら、社員参加型の活動機会を増やしていく方針だという。
また、広田は、支援している活動は極力現地まで行って自分の目で見るようにしている。例えば、先述の石川県河北潟のプロジェクトがそうだ。能登半島地震のことは知っていたが、いざ現場に行くと足がすくむような光景が広がっていた。
「震災による道路の陥没やゴミの堆積など生々しい現場を見ました。これほどのダメージを一体どうやって元に戻していくのか、この惨状をどのように社会に届ければいいのか、考えさせられる光景で、気が遠くなるような想いにもなりました……。ただ目の前では、皆さん、自分ができることをやろうという想いで活動を進めていたんですね。ならば、キヤノンMJグループもできることを重ねていこうと、改めて決意しました」
人の営みがある以上、求められる社会貢献も変わっていくだろう。社会貢献は持続的に進化させるべき取り組みだ。その時その時に、キヤノンMJグループができることを最大限実行していくため、活動そのものの工夫や提供価値の充実はもとより、新しいプロジェクトも積極的に進めていきたいと広田は言う。穏やかな印象の広田だが、社会貢献活動と向き合うその目には確かな使命感と情熱が宿っている。

本記事に関するアンケートにご協力ください。
2分以内で終了します。(目安)

